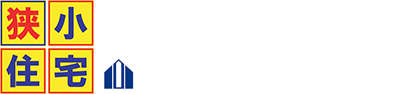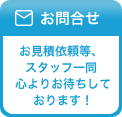静岡市清水区三保 H様邸新築現場-7 「BM」→「遣り方」→「水糸」
基礎工事がスタート。
先日の地鎮祭の時に 建物の位置の最終確認を行い白いロープを張っておきました。
四方に木組みをします。これをやり方と呼びます。
やり方とは、漢字で書くと【遣り方】
私、工業高校の建築科に入った時に 教科書の一番最初に出てきました。
入学式の次の日、1ページ目でしたからこれ【だけ】は記憶にあります。。。その他は記憶にない(笑)
この木枠を建物の四つ角に組んで、ナイロン製の糸を水平に張ります。
基礎を造る時、やみくもに掘ったら 深すぎても浅すぎても困るわけで・・・
底面の高さを隈なくチェックしながら掘り進める 基準となる大事な作業。
杭の名前は【水杭】 杭同士を繋ぐ板の事を【水貫】といいます。
【BM±0】という印。
これから建築する上で 高さの基準は全てココからスタートします。 BMはベンチマークの略です。
基準点なので動く物・・・例えばプランターとか置いてあるブロックは絶対NG!
途中で動かされちゃうと 基礎の底面や平均地盤高さ、床の高さ(FL:フロアライン)の算出が不可能になる訳です。
今回は敷地と道路の境にある境界線プレートに貼らせてもらいました。
境界の【⇩】動かす人はいませんからね♪
砕石の搬入。 黒い【土】のように見えますが 実は細かく砕いた【岩】
基礎の下にこれを敷き詰める事で表面が締め固まり強度が増します。
防湿シートで覆います。
基本この辺りは砂地ですから、それ程湿気の心配はないのですが
地面からの湿気やシロアリが上がってこないようにシートでシャットアウト!
その周りに捨てコンという、コンクリートで固めます。
捨てコンは 基礎のコンクリではなくこれから鉄筋を組むための舗装の役割を果たします。
捨コンの上にピンッ! と張った黄色いナイロン紐見えますか?
水糸で(みずいと)です。
このラインが外壁の芯(中心)になるので鉄筋やボルトをセットする時の測点。
高さも全て水平になっていますから左右上下の基準となります。