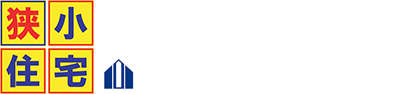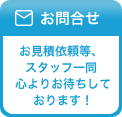静岡市清水区三保 H様邸新築現場-8 ベタ基礎の鉄筋を組んでいます
ベタ基礎の鉄筋組みが始まりました。
まずは外周に型枠を組んで 建物の位置出し&直角を確定させます。
『直角』←これ90度。 大事です。 91度でも89度でもOUT。歪んだ家になってしまいます。
息子が少年野球やってた頃、試合の日はお父さん達が ホーム→1塁→2塁→3塁のベースの位置をメジャーで測って決めるんですけど・・・
これがなかなか難しい。菱形になったり 台形になってしまうんです。
そーゆー時は私がしゃしゃり出て3:4:5(さしご)を伝授♪
これは 辺の長さ3m、4m、5mの三角形を地面で作ると3と4が交わる角が必ず90度になる測量法。
実際野球の場合には9m:12m:15mと大きくした方が正確。誤差が出にくいです。
と・・・言いつつも 工事現場では測量器が進化してますので3:4:5は使ってません(笑) 豆知識書いといて、実際は使ってない無駄話なのだ。。。
基礎のコーナー部分は大事です。
大型地震の激震の時は、建物の角に衝撃が集中して歪んだり 破壊が始まるので
鉄筋もしっかり重ねて二重に組んで頑丈にします。
次に耐圧ベース。
おぼん、でいうところの 一番下の部分。地面と接触する底面。ココにもクロスさせながら鉄筋を組んでいきます。
最初に【X軸方向】 建築の世界でもにも【X】や【Y】が頻繁に出て来ます。
中学の数学から【X】とか【Y】の記号って出てきましたよね?
自分、あの辺りっから勉強嫌いになりました(笑)
だいたいが意味不明のXとYに二乗したり三乗すること自体
身体が拒否反応起こしてましたから!
設計図を置いて見た時、上下に向かって書いてある線や材料、壁方向を【Y軸】と言い【X軸】はそれに直交して取り付ける部材の事。
今日はYが先で、その後からX方向の鉄筋を組んだ事になります。
このコンクリの破片。ゴミではありません。 これ基礎工事では重要。
みんな【サイコロ】って呼んでますが 本当はスペーサーっていうものです。
基礎は建物の荷重の全てを受け止める部分で強くなければなりません。
コンクリートの基礎の強度は、中の鉄筋がしっかり コンクリ厚の真ん中に入っているか?です。
地面に置いただけの鉄筋の上から コンクリートをダラダラ流しても意味がありません。
スペーサーを下に挟み込んで 鉄筋を浮かせる事でコンクリが上下にしっかり流れ込んで包み込んでこそ、耐震強度が高まります。
あ・・・思い出した! とっても嫌な記憶がよみがえってきました。
さっきのグランドで子供の野球のベースの位置出す時。。。
私が『さしご』で辺の長さ3m、4m、5mの三角形を地面で作ると3と4が交わる角が必ず90度になる測量法。
これをお父さん達みんなで巻尺で測っていたらねっ! 「√(ルート)を使った方が全然早いし正確だ!」という理系パパがいたんです。
『さしごで出すのは古代だと!? 今はルート」と異議を唱えられたのです。
要するにホームから1塁まで23m ホームから3塁も同じ23m。 なので√23を導き出せば簡単に1→3塁間の距離も出るし 必然的に直角二等辺三角形だから角度も90度に揃えられるというのである。。。
確かに! 完璧だ。 ぐ~の音も出ない@o@;/
でもね√23って・・・計算機誰か持ってる? 32.52m? 巻尺長さ50mの1個しかないから、23m→23m→32.5mを同時にはポイント落とせないんですよ~
だから(3:4:5)を 9m:12m:15mに流用して40m程の巻尺で大人3人でサクサクと直角出していたのです。